 |
 |
| 佐倉のみのりの里。風車が見える |
宗吾参道駅。小さい駅だ。 |
 |
 |
| 宗吾参道駅から、義民ロードという道があるのだ。 |
 |
 |
 |
宗吾霊堂に来た。ここのお寺には、佐倉藩家老の暴政を徳川家4代将軍家綱に直訴し、処刑された佐倉宗吾(木内惣五郎)の親子が祀られている。昔は、直訴はご法度の中、死を覚悟で領民を願いを背負って直訴した素晴らしい領民がいるのだ。以下、ネットより。
当山は宗吾霊堂と呼ばれ広く知られていますが、正しくは鳴鐘山東勝寺宗吾霊堂といいます。
境内は木々の緑につつまれ、春の花見に秋の紅葉にと年中人出が絶えません。
約10万平方メートルの広さに、年間参詣者は約250万人の人々が訪れる霊場です。
当山の縁起は桓武天皇の時代に、征夷大将軍 坂上 田村麻呂が房総を平定し、戦没者供養のため建立された真言宗豊山派の寺院です。
我が国の代表的義民として有名な佐倉宗吾(本名 木内 惣五郎)様は、今から350年前に佐倉藩国家老による暴政のため領民の救済を4代将軍 家綱公へ直訴し、その罪により公津ケ原刑場で磔刑(はりつけ)に処せられました。
この時、当山の住僧 澄祐(ちょうゆう)和尚は遺骸を刑場跡に埋葬されました。
現在のお墓がそれで惣五郎様の処刑後、佐倉藩はその失政を悔い、宝暦2年(1752年)、百回忌の時に堀田 正亮(まさすけ)公は宗吾道閑居士の法号を諡号しました。
以来、惣五郎様は宗吾様と呼ばれるようになり、寛政3年(1791年)、堀田 正順(まさなり)公は徳満院の院号と石塔一基を寄進しました。
文化3年(1804年)には堀田 正時(まさとき)公が惣五郎様の子孫に田高5石を供養田として与えました。
長い間、宗吾様をまつる堂宇の建立は許されませんでしたが、現在は本堂・客殿・霊宝殿・仁王門・鐘楼堂・宗吾様の御生涯を66体の等身大の人形により再現した日本有数の大パノラマ式の宗吾御一代記館等の建造物があり、信仰に参詣に多くの人々の人気を博しています。 |
 |
 |
| 宗吾街道、直訴街道とも呼ばれている。 |
麻賀多神社についた。パワースポットの雰囲気。 |
 |
麻賀多神社の本殿。以下、ネットよりご由緒。
その昔日本武尊東征の折 この地方の五穀の実りが悪いのを知り 里人を集め大木の虚に鏡を掛け その根本に七つの玉を埋めて伊勢神宮に祈願いたしましたところ その後は豊年がつゞきました 又三世紀の頃 印旛国造伊都許利命は この御鏡を霊代として祀られる 稚日霊命の霊示をうけ 玉を堀り御霊代として 稚産霊命(伊勢外宮の親神)を祀り 麻賀真の大神と崇め 八代神津の両郷を神領として奉斎しました その後推古天皇十六年(608年)新に宮居をこの地に建て 麻賀多の大宮となづけました
本地御鎮座以来一千三百六十余年 印旛郡下十八麻賀多の総社として 筒粥祭 御田植祭 豊年神楽などの古い儀式が継承され御祭神にゆかりのある古い地名等も現存しています 又明治五年に郷社に 昭和十年御神本大杉は 県の天然記念樹に 更に近年 御本殿は市の文化財に 神域は史跡に撰ばれ 産業 開運 長寿 厄除けの守護神として崇められていることはよく知られています |
 |
| そしていよいよ日月神示が降りた天日津久神社。 |
 |
| この神社には大杉もある。樹齢1300年? |
 |
 |
| 佐倉宗吾の生家。 |
 |
| 次に甚平の渡しに向かう。沼地と田園が広がる。 |
 |
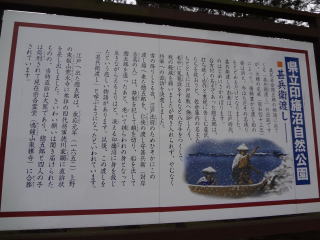 |
 |
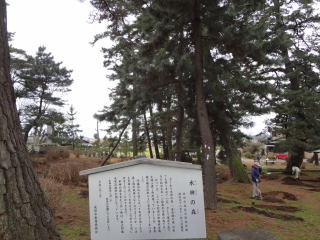 |
 |
甚平の渡しには松林、水神が祀られている。印旛沼が干拓される前までは、ここまで海岸線があったという。以下、佐倉宗吾の直訴を、手助けした渡し守の甚平の碑。
台方村の名主(なぬし)であった佐倉惣五郎(さくらそうごろう)は、打ち続く凶作と重税に苦しむ農民たちを救おうと佐倉藩内の名主たちと一緒に江戸屋敷へ強訴したりして税の軽減を願い出ましたが聞き入れられず、やむなく将軍への直訴(じきそ)を決意しました。
雪の降りしきる夜、江戸出府のため密かに、この渡し場に来た惣五郎を任侠の渡し守、甚平は、禁制を犯して鎖を切り、舟を出して惣五郎を送った後、老いて捕らわれの身となって生きながらえるよりはと、凍(こご)える印旛沼に身を投じたという悲しい物語があります。 |
 |
 |
もう一つの麻賀多神社(船方)に行く。この隣には、 印波国造伊都許利命の古墳。以下、ネット。
この古墳は、「先代旧事本記」の中の「国造本記」に見える“印波国造伊都許利命”の墳墓と伝えられている。
伊都許利命は、神武天皇の皇子神八井命の8代目の御孫で、応神天皇の命を受けて、印旛国造としてこの地方を平定され、産業の指導などに多くの功績を残す。
その昔、日本武尊東征の折り、大木の虚に鏡をかけ、根本に7つの玉を埋めて、伊勢神宮に祈願した。命は、「この鏡を崇め祀れば長く豊作が続く」との教えを聞き、その鏡をご神体として、この地に稚日霊命を祀り、その後、霊示によって7つの玉を掘り出して稚産霊命を祭り、共に麻賀多真大神として里人の崇敬を指導されてから、年々豊作と楽土が続いた。
|
 |
 |
| 赤坂公園で基本、型、補強。 |
成田駅に向かうと、新興住宅街。 |
 |
 |
| 成田山の参道。正月の時より人は少ないが、それでも結構多い。 |
 |
 |
 |
 |
 |
成田山新勝寺。以下、ネットより由緒。
成田山新勝寺は、天慶3年(940年)寛朝大僧正によって、開山されました。寛朝大僧正は、朱雀天皇より平将門の乱平定の密勅を受け、弘法大師が敬刻開。眼された不動明王を奉持し難波の津の港(現大阪府)より海路を東上して尾垂ヶ浜(千葉県
山武郡横芝光町)に上陸、更に陸路を成田の地に至り、乱平定のため平和祈願の護摩を奉修し成満されました。大任を果たされた大僧正は再び御尊像とともに都へ帰ろうとしましたが不思議にも御尊像は磐石のごとく微動だにしません、やがて「我が願いは尽くる事なし、永くこの地に留まりて無辺の衆生を利益せん」との霊告が響きました。
これを聞いた天皇は深く感動され、国司に命じてお堂を建立し「新勝寺」の寺号を授与し、ここに東国鎮護の霊場として「成田山」が開山されました。
|